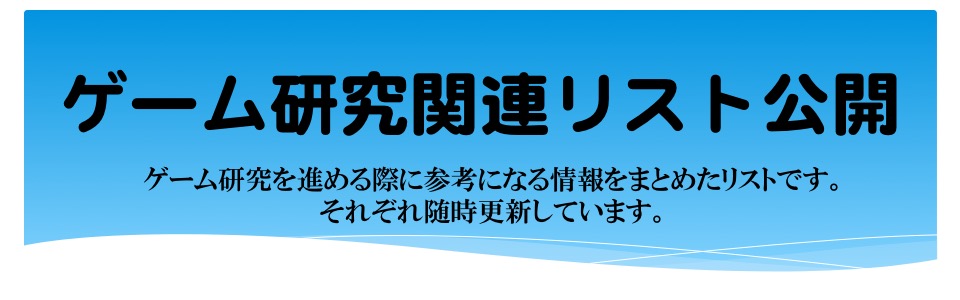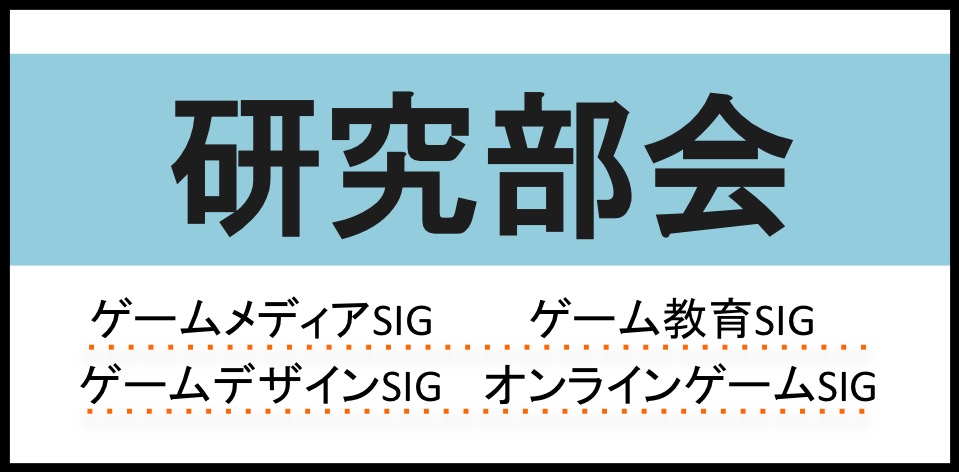- 2009年5月28日 DCAJ『デジタルコンテンツ制作の先端技術応用に関する調査研究報告書』を公開
- 2009年5月8日 ゲーム学再考−ゲーム学とDiGRA JAPANに期待すること−(DigraJ公開講座09年4月期)
- 2009年4月2日 学会事務業務の外部委託について
- 2009年3月9日 公開講座「名人の目から見たファミコンブーム」メディア掲載情報
- 2009年3月6日 名人の目から見たファミコンブーム(DigraJ公開講座09年2月期)
- 2009年3月4日 後援イベント 「ゲーム産業の拠点を目指す福岡の挑戦」開催報告
- 2009年2月7日 学会誌『デジタルゲーム学研究』販売のご案内
- 2009年1月22日 不可能を可能にするゲームデザイン(DigraJ公開講座09年1月期)
- 2008年12月20日 「オンラインゲームの教育利用〜なぜオンラインゲームは教育に役立つのか?」日韓国際シンポジウム
- 2008年11月28日 囲碁AIにおける革命「モンテカルロ木探索」とは何か?(DigraJ公開講座08年11月期)
関連イベントのお知らせ
- 2013年7月3日 夏季研究発表大会 ポスター発表募集のお知らせ
- 2013年6月15日 第6回DiGRA-K交流会&勉強会開催。今回のテーマは『まちつく!』と『ウィザードGPS』のクリエイターを招いた「位置ゲー」
- 2012年2月25日 日本デジタルゲーム学会2011年度年次大会
- 2011年7月17日 日本デジタルゲーム学会第三回研究会: ゲームデザイン研究会(第二回)開催のお知らせ
- 2011年5月14日 日本デジタルゲーム学会第二回研究会(5月14日)
事務局からのお知らせ
- 2016年5月30日 日本デジタルゲーム学会
- 2013年7月3日 夏季研究発表大会 ポスター発表募集のお知らせ
- 2013年6月28日 日本デジタルゲーム学会選挙について
- 2013年6月18日 学会選挙規定一部改定のお知らせ
- 2013年6月15日 DiGRA Japanニューズレター65号
投稿日:2009年5月28日
財団法人デジタルコンテンツ協会(DCAJ)『デジタルコンテンツ制作の先端技術応用に関する調査研究報告書』が、WEBサイトにて公開されました。
◆報告書本文(PDF:8.74MB)
http://www.dcaj.org/report/2008/data/dc_08_03.pdf
本報告書では、ゲームプラットフォームの変遷、ゲーム開発技術ロードマップ、国内のゲーム関連技術教育、GDCにおける海外のゲーム関連技術、IGDAカリキュラムフレームワーク2008の邦訳、日本のゲーム関連技術教育についての課題と提案などがまとめられています。目次は以下のとおりです。
第1章 はじめに……1
1.1 調査研究の目的……1
1.2 本年度の活動……1
1.2.1 第1回委員会……2
1.2.2 第2回委員会……2
1.2.3 第3回委員会……2
1.2.4 第4回委員会……2
1.2.5 第5回委員会……3
1.2.6 第6回委員会……3
1.2.7 セミナー「IGDAカリキュラムフレームワーク紹介およびGDC09報告会」……3
1.3 推進体制……3
第2章 ゲーム・プラットフォームの変遷……5
2.1 ゲーム・プラットフォームの変遷……5
2.1.1 1970年代におけるゲームプラットフォーム……5
2.1.2 1980年代におけるゲーム・プラットフォーム……5
2.1.3 1990年代におけるゲーム・プラットフォーム……7
2.1.4 2000年代におけるゲーム・プラットフォーム……9
2.2 ゲーム・プラットフォームの概要……11
2.2.1 ファミリーコンピューター……11
2.2.2 PCエンジン……12
2.2.3 メガドライブ……12
2.2.4 ゲームボーイ……13
2.2.5 ネオジオ……14
2.2.6 ゲームギア……15
2.2.7 スーパーファミコン……16
2.2.8 3DO REAL……16
2.2.9 セガサターン……17
2.2.10 PlayStation……18
2.2.11 NINTENDO64……18
2.2.12 ドリームキャスト……19
2.2.13 ワンダースワン……20
2.2.14 PlayStation2……21
2.2.15 ゲームボーイアドバンス……22
2.2.16 NINTENDO GAMECUBE……22
2.2.17 Xbox……23
2.2.18 ニンテンドーDS……24
2.2.19 プレイステーション・ポータブル……25
2.2.20 Xbox 360……26
2.2.21 PLAYSTATION3……27
2.2.22 Wii……27
第3章 ゲーム開発技術ロードマップ……29
3.1 はじめに……29
3.2 カテゴリー別の技術ロードマップ……32
3.2.1 技術としてのゲームデザイン……32
3.2.2 素材作成 CG(3D)……50
3.2.3 素材作成 サウンド……57
3.2.4 素材作成 アニメーション……62
3.2.5 プログラミング AI……73
3.2.6 プログラミング グラフィックス描画……137
3.2.7 プログラミング 物理・衝突判定……154
3.2.8 タスクシステム 技術詳細編……162
3.2.9 タスクシステム 技術遷移編……173
3.2.10 プログラミング スクリプト……183
3.2.11 ネットワーク通信……192
3.2.12 開発方法論と、その歴史……213
第4章 国内のゲーム関連技術教育についての調査……230
4.1 変容する日本のゲーム産業と人材マネジメント……230
4.1.1 目的と背景……230
4.1.2 方法とデータの概要……231
4.2 経営環境の変化……233
4.2.1 事業領域……233
4.2.2 プラットホーム別年間出荷タイトル数……234
4.2.3 2006年度の業績(対前年度比))……234
4.2.4 経営環境の変化に対する認識……235
4.2.5 ゲーム産業における経営戦略……236
4.3 開発者の獲得……237
4.3.1 開発者の確保……237
4.3.2 雇用形態別雇用量の増減……238
4.3.3 人材ポートフォリオ……238
4.3.4 開発者採用フローの事例……240
4.3.5 開発者採用上の問題点……240
4.4 開発者の育成とキャリアディベロップメント……241
4.4.1 開発者の育成に対する考え方……241
4.4.2 開発者のキャリアディベロップメント……242
4.4.3 開発者の育成上の問題点……249
4.5 開発者の評価……249
4.5.1 開発者の評価に対する考え方……250
4.5.2 開発者の評価制度の事例……250
4.5.3 開発者の評価上の問題点……251
4.6 開発者の処遇……252
4.6.1 開発者の処遇に対する考え方……252
4.6.2 開発者の賃金制度改革……253
4.6.3 開発者の処遇制度の事例……253
4.6.4 開発者の処遇上の問題点……254
4.7 要約と結論……254
4.7.1 要約……255
4.7.2 結論……256
4.8 残された課題……258
4.9 ゲーム関連技術教育についてのヒアリング……261
4.9.1 株式会社セガ……261
4.9.2 株式会社バンダイナムコゲームス……272
4.9.3 フロム・ソフトウェアにおける社内ゲームAIセミナーの紹介……284
4.10 ゲーム開発技術の歴史についてのヒアリング……301
第5章 GDCにおける海外のゲーム関連技術についての調査……331
5.1 はじめに……331
5.2 PlayStation 3 における SPUの使用法……334
5.2.1 Insomniacの PlayStation3 Programming講座……334
5.2.2 GOD OF WAR における SPU の利用……339
5.2.3 KILLZONE 2 におけるSPUの使用法……342
5.3 レンダリングの新しいトレンドとシェーディングの新しいトレンド……352
5.3.1 Deferred Renderer と Light Pre-pass Renderer……352
5.3.2 Resistance2 におけるPre-rendering とdeferred-rendering……353
5.4 グローバル・イリュミネーション……355
5.5 キャラクターアニメーションの精緻化とメタAI……356
5.5.1 キャラクターアニメーションの精緻化……357
5.5.2 メタAI……356
5.6 プロシージャル技術……357
5.6.1 HALO WARS における地形自動生成……357
5.6.2 LOVE におけるオール・プロシージャルな世界……359
5.6.3 セミ・プロシージャルというアプローチ……361
5.7 インディーズ・ゲームにおける技術とゲームデザインの融合……364
5.8 References……367
第6章 海外におけるゲーム関連技術教育のマニュアル……370
6.1 「IGDAカリキュラムフレームワーク2008」の翻訳意図について……370
第7章 日本のゲーム関連技術教育についての課題と提案……372
7.1 ゲーム関連技術教育の現状と課題……372
7.1.1 ゲーム関連技術の編纂と蓄積……372
7.1.2 ゲーム関連技術の歴史的俯瞰と国内外の動向……372
7.1.3 ゲーム関連技術教育の現状……373
7.1.4 ゲーム関連技術教育の課題……374
7.2 ゲーム関連技術教育についての提案……376
7.2.1 新卒採用者に対するゲーム関連技術教育の提案……376
7.2.2 中途採用者に対するゲーム関連技術教育の提案……376
7.2.3 経験からの学習の促進の提案……377
7.2.4 語学教育とOff-JTの提案……377
7.2.5 カリキュラムフレームワークの邦訳とその活用の提案……377
7.2.6 ゲーム関連開発技術教育とキャリアに関する提案……378
参考資料 IGDAカリキュラムフレームワーク日本語訳……379
投稿日:2009年5月8日
ゲーム学再考−ゲーム学とDiGRA JAPANに期待すること−
(DigraJ公開講座09年4月期
2009年5月8日(金) 18:00 開始
過去2回、学生会員を中心としてゲーム学に関するラウンドテーブルを実施してきました。学会も4年目に入り、また規模も拡大しております。
ここで、再びゲーム学とは何か、そして、そこにおいて学会が果たす役割は何か、ということについて、広く意見を交わしたいと思います。
参加者定員が多いため、なかなか発言の機会が回らないこともあるとは思いますが、産業界・学術界、あるいは学生の皆様からの積極的な発言をお待ちしております(あまり詳しくないけれど、興味はある、という方はもちろん無理にご発言を頂くことはありませんので、気軽にご参加ください)。
まず初めに、モデレーターからのいくつかの問題提起の後、自由に議論を行いたいと考えております。
※当日の学会入会および年会費の支払いは受け付けておりません。
※4月公開講座ですが、会場の都合により5月開催となります。ご了承ください。
<概要>
■講師:
ラウンドテーブル形式で行います
■タイトル:
「ゲーム学再考−ゲーム学とDiGRA JAPANに期待すること−」
■開催日時:
2009年5月8日(金) 18:00開始 20:00終了
※都合により、開催日が4月末から5月初旬へ変更されております。ご注意下さい。
■場所:
東京大学本郷キャンパス 工学部新2号館9階92B教室
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_03_j.html
■定員:
50名 (予約が満席の場合は、当日参加受付はございません。)
■参加費:
無料
※今回はラウンドテーブル形式のため、参加費は非会員の方も無料となっております。
※当日の学会入会は受け付けておりません。
投稿日:2009年4月2日
2008年度理事会・年次総会で決定したとおり、日本デジタルゲーム学会の事務業務を2009年3月下旬より、順次、外部委託しております。委託先は、以下のとおりです。
株式会社ガリレオ 東京オフィス 学会業務情報化センター内 日本デジタルゲーム学会事務局
〒170-0004 東京都豊島区北大塚3-21-10 アーバン大塚3F
TEL:03-5907-3750
FAX:03-5907-6364
E-mail : g012digra_j-mng [at] ml.gakkai.ne.jp
URL:http://www.galileo.co.jp/
学会事務業務の外部委託が完全移行された際には、会員各位は、オンライン上で各自の登録情報(連絡先・会費納入情報・学会誌発送情報)を確認していただくことができます。また、各自の登録情報(連絡先)変更もオンライン上で行うことができます。
本サービスは、会員各位へIDとPWを発行後、ホームページにて告知の上、開始いたします。
サービス開始まで、今しばらくお待ちください。
投稿日:2009年3月9日
2009年3月6日(金)、東京大学大学院情報学環・福武ホール・福武ラーニングシアター(東京都文京区本郷7-3-1)において本学会主催にて開催された公開講座 「名人の目から見たファミコンブーム」について、ウェブメディアにて掲載されましたのでご紹介いたします。
■ファミ通.com(2009年3月7日掲載)
ハドソン高橋名人が、東京大学で“ファミコンブーム”を熱く語る!
http://www.famitsu.com/game/news/1222608_1124.html
■毎日jp まんたんウェブ(2009年3月8日掲載)
高橋名人:東大でファミコンブームの内幕を講演 「ゲームは1日1時間」が問題に?http://mainichi.jp/enta/mantan/news/20090307mog00m200016000c.html
■ITmedia(2009年3月12日掲載)
“高橋名人”という社会現象——高橋利幸氏、ファミコンブームを振り返る(前編)
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0903/12/news087.html
■ITmedia(2009年3月13日掲載)
16連射、ゲームは1日1時間の裏側——高橋利幸氏、ファミコンブームを振り返る(後編)
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0903/13/news009.html
投稿日:2009年3月6日
名人の目から見たファミコンブーム
(DigraJ公開講座09年2月期
2009年3月6日(金) 18:00 開始
※受付の都合により、非会員の方の参加費が3,000円から1,000円に変更になりました。混乱を招き、ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございませんが、ご了承ください。
2009年2月の公開講座では、株式会社ハドソンより高橋利幸氏を講師に招き、日本におけるゲーム文化がどのような変遷を遂げてきたのかを、「名人」という立場でゲーム文化を牽引してきた氏の視点から、ご講演頂く予定です。
※都合により、開催日が2月末から3月初旬へ変更されております。ご注意下さい。
開発者のみならず、研究者の皆様にも非常に意義深い講演になると存じますので、皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。
<概要>
■講師:
高橋 利幸
(株式会社ハドソン 名人)
http://www.16shot.jp/index.html
■タイトル:
「名人の目から見たファミコンブーム」
■開催日時:
2009年3月6日(金)18:00開始 20:00終了
※都合により、開催日が2月末から3月初旬へ変更されております。ご注意下さい。
※受付開始時間は17:30です。非常に混雑が予想されますのでお早目のご来場をお願いいたします。
■場所:
東京大学本郷キャンパス 福武ラーニングシアター
(福武ホール地下2階)
(地図)http://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/access.html
■定員:
180名 (予約が満席の場合は、当日参加受付はございません。また、当日参加の方は受付でお待ち頂く場合がございます。ご了承下さい。)
■参加費:
日本デジタルゲーム学会 正会員?学生会員:無料
日本デジタルゲーム学会 賛助会員(一口あたり代表者3名まで):無料
非会員:3,000円
1,000円
(当日 受付にてお支払いください)
※参加費が3,000円から1,000円に変更になりました。
※当日の学会入会は受け付けておりません。入会を希望される方は、必ず開催前々日までに会員登録及び年会費の振り込みを完了させてください。
※なお、本公開講座参加申し込み時に会員ではなくても、開催日までに当学会に入会される方は、本公開講座の参加申し込みの際には会員としてご登録ください。
※開催日の前々日までに会員登録および年会費納入のご連絡が確認出来ない場合は、非会員とみなし、参加費3,000円を頂戴いたします。
※領収書の宛名につきまして、参加登録者名義と異なる場合は必ず申し込みフォームにご入力ください。特に入力がない場合、登録されたご氏名にて領収書が発行されます。当日その場での領収書の発行には応じられない可能性がございますので、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009年3月4日
2009年1月23日(金)、ソラリア西鉄ホテル(福岡市)において本学会後援にて開催されたシンポジウム 「ゲーム産業の拠点を目指す福岡の挑戦」について、総合研究開発機構(NIRA)のウェブサイトにて掲載されましたのでご紹介いたします。
◆2009年3月2日掲載
NIRA地方シンクタンク・ワークショップ開催報告「ゲーム産業の拠点を目指す福岡の挑戦」http://www.nira.or.jp/outgoing/symposium/entry/n090302_317.html
投稿日:2009年2月7日
日本デジタルゲーム学会(DiGRA JAPAN)では、学会誌『デジタルゲーム学研究』を毎年発行し、年会費を納められている会員各位(正会員・学生会員・賛助会員)には、当該年度の学会誌を送付しております。
会員でバックナンバーをご覧になりたい方、非会員で学会誌をご覧になりたい方などの需要に応えるために、販売も行っております。
デジタルゲーム学にご関心をお持ちの方々(個人、企業、大学、研究所等)は、ぜひともご購入いただければ幸いです。
詳細は、以下のURLをご参照ください。
http://www.digrajapan.org/modules/tinyd5/index.php?id=2
■販売価格
日本デジタルゲーム学会会員……3,000円(送料・税込)
日本デジタルゲーム学会非会員…5,000円(送料・税込)
■学会誌の購入方法
(1)学会誌購入申込書のご送付
学会誌購入申込書を事務局にご送付ください。
▼
(2)学会誌購入代金のお振り込み
学会誌購入申込書を事務局に送付後、代金を学会指定の口座に2週間以内にお振込みください。
▼
(3)学会誌の送付
学会誌購入申込書が事務局に届き、入金を確認後、学会誌を送付いたします。
投稿日:2009年1月22日
不可能を可能にするゲームデザイン
(DigraJ公開講座09年1月期)
2009年1月22日(木) 18:00 開始
2009年1月の公開講座では、株式会社コナミデジタルエンタテインメントより小島秀夫氏を講師に招き、小島氏のゲーム開発のコンセプトや小島氏が監督として開発を手掛けられているメタルギアシリーズの開発秘話などについてご講演頂きます。
開発者のみならず、研究者の皆様にも非常に意義深い講演になると存じますので、皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。
※今回の公開講座では写真?ビデオの撮影および録音は禁止させて頂きます。
※今回の公開講座ではメディアの取材はお断りさせて頂いております。ご了承下さい。
<概要>
■講師:
小島 秀夫
(株式会社コナミデジタルエンタテインメント/小島プロダクション)
http://www.konami.jp/kojima_pro/japanese/index.html
■タイトル:
「不可能を可能にするゲームデザイン」
■開催日時:
2009年1月22日(木)18:00開始 20:00終了
※通常の公開講座と異なり、開催曜日が木曜日となります。ご了承ください。
※受付開始時間は17:30です。非常に混雑が予想されますのでお早目のご来場をお願いいたします。
■場所:
東京大学本郷キャンパス 福武ラーニングシアター
(福武ホール地下2階)
(地図)http://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/access.html
■定員:
180名 (予約が満席の場合は、当日参加受付はございません。また、当日参加の方は受付でお待ち頂く場合がございます。ご了承下さい。)
■参加費:
日本デジタルゲーム学会 正会員?学生会員:無料
日本デジタルゲーム学会 賛助会員(一口あたり代表者3名まで):無料
非会員:3,000円
(当日 受付にてお支払いください)
※当日の学会入会は受け付けておりません。入会を希望される方は、必ず開催前々日までに会員登録及び年会費の振り込みを完了させてください。
※なお、本公開講座参加申し込み時に会員ではなくても、開催日までに当学会に入会される方は、本公開講座の参加申し込みには会員としてご登録ください。
※開催日の前々日までに会員登録および年会費納入のご連絡が確認出来ない場合は、非会員とみなし、参加費3,000円を頂戴いたします。
※領収書の宛名につきまして、参加登録者名義と異なる場合は必ず申し込みフォームにご入力ください。特に入力がない場合、登録されたご氏名にて領収書が発行されます。当日その場での領収書の発行には応じられない可能性がございますので、よろしくお願いいたします。
投稿日:2008年12月20日
「オンラインゲームの教育利用
〜なぜオンラインゲームは教育に役立つのか?」
日韓国際シンポジウム
(Why are Online Games Useful for Education?)
入場無料
2008年12月20日(土) 0:00 受付終了
独立行政法人科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業(CREST)「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」領域(研究総括:原島博[東京大学])では、「オンラインゲームの制作支援と評価」が取り組まれています。
その一環として、東京大学大学院情報学環・馬場章グループは、2008年12月20日(土)、「オンラインゲームの教育利用〜なぜオンラインゲームは教育に役立つのか?」日韓国際シンポジウムを、東京大学本郷キャンパスにて開催いたします。
本シンポジウムでは、教育を目的としてオンラインゲームを利用し、その科学的評価を行っている日韓の研究グループの成果を持ちよります。そしてこのような研究成果を、研究者のみならずゲーム開発者や小・中・高校の教師や保護者の方々と共有し、オンラインゲームとシリアスゲームの新たな可能性を多角的・実践的に検討することで、教育目的の新たなデジタルゲーム、とりわけオンラインゲームの開発と積極的な普及・利活用につなげることを目指します。
本シンポジウムは、日韓のオンラインゲームの教育利用研究を集約する、日本では初めて開催のシリアスゲームの国際学術シンポジウムとなります。研究者・ゲーム開発者・教師・保護者の方々をはじめ、デジタルゲーム・オンラインゲーム・シリアスゲームの研究・開発・ビジネスにご関心をお持ちの方々にご参加をいただきますようご案内申し上げます。
※詳細につきましては、シンポジウム公式サイトをご覧ください。
http://chi.iii.u-tokyo.ac.jp/crestsympo/
※日本デジタルゲーム学会の12月公開講座につきましては、本シンポジウムを持って振り替えとさせて頂きます。
ご了承下さいますよう、宜しくお願いいたします。
※参加申込は、本ページよりお願い致します。
<概要>
■開催日時:
2008年12月20日(土) 14:00〜17:20 (受付開始13:30)
■場所:
東京大学本郷キャンパス 福武ホールB2F 福武ラーニングシアター
http://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/access.html
■予定:
13:30 受付・入場
14:00 開会挨拶
松原 仁 (公立はこだて未来大学システム情報科学部・教授)
14:05 講演 「歴史教育におけるオンラインゲームの活用」
馬場 章 (東京大学大学院情報学環・教授、DiGRA JAPAN 会長)
14:35 講演 「社会性の向上をもたらすオンラインゲームの活用」
坂元 章 (お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科・教授、
DiGRA JAPAN 副会長)
14:55 講演 「ゲーム産業戦略とゲームの社会的認知、活用の現在」
野澤泰志 (経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課・課長補佐)
15:10 休憩
15:20 講演 「効果的な教育ツールとしてのオンラインゲーム」
ウィ・ジョンヒン (ソウル中央大学経営戦略学科・教授、
コンテンツ経営研究所・所長)
15:45 講演 「小学校の英語教育におけるMMORPG を用いた授業」
ソ・スンシク (春川教育大学コンピュータ教育学部・准教授)
16:05 講演 「韓国における政策支援とその課題」
ユー・ビョンチェ (文化体育観光部文化産業振興課ゲーム産業チーム・課長)
16:20 休憩
16:30 オープンディスカッション
「なぜオンラインゲームは教育に役立つのか?」
坂元 章、野澤 泰志、ウィ・ジョンヒン、ソ・スンシク、ユー・ビョンチェ、
馬場 章(司会)
17:10 閉会挨拶
馬場 章
17:20 閉会
■定員:
180名
■参加費:
無料 (当日、プロシーディングスを配布します)
■使用言語:
日本語・韓国語の同時通訳
■主催:
東京大学大学院情報学環
「オンラインゲームの教育目的利用のための研究」グループ(研究代表:馬場章)
独立行政法人 科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業(CREST)
「デジタルメディア作品の制作を支援する基盤技術」領域(研究総括:原島博)
「オンラインゲームの制作支援と評価」チーム(研究代表:松原仁)
■共催:
日本デジタルゲーム学会(DiGRA JAPAN)
■お問い合わせ先:
東京大学大学院情報学環 馬場章研究室(担当:馬場章・藤原正仁)
住 所 : 113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
E-mail : crestsympo2008 [atmark] ml.infoseek.co.jp
TEL/FAX : 03(5841)8767
投稿日:2008年11月28日
碁AIにおける革命「モンテカルロ木探索」とは何か?
(DigraJ公開講座08年11月期)
2008年11月28日(金) 12:00 受付終了
追加情報: 当日の発表資料は、ダウンロードページにて公開しています。
デジタルゲームにおいて必要とされる人工知能には、主に
(i) 連続的な空間でリアルタイムに進行するAI
(ii) 離散的な空間(例えばマス目やヘキサグラムで区切られた空間上)でターン制で進行するAI
に区別されます。
後者のボードゲームにおける人工知能は、ゲームAIの歴史にとっても、人工知能の歴史にとっても、その発祥から続く長い研究の歴史のある分野であり、さらにその中においても、チェス、将棋、囲碁におけるAIは、その深いゲーム性ゆえに研究者の意欲を喚起し、歴史的に継続して研究され、進化して来た分野です。
ところが近年、将棋においては「ボナンザ法」、囲碁においては「モンテカルロ木探索」という革新的な手法が発見され、この分野の開発者・研究者に大きな衝撃を与えました。特にコンピュータ囲碁界においては、CrazyStoneとMoGoの与えたインパクトは長年(15年程度)の停滞を一気に打ち破る、非常に大きなブレイクスルーでした。最も手数が多く難解とされて来た囲碁において、限定した9路盤(9x9に制限した囲碁盤)上とは言え、「モンテカルロ木探索」によって初めてプロ棋士に勝利したというニュース(2008年)が、世界中のゲームAI関係者に強い衝撃を与えました。
「モンテカルロ木探索」とは、非常に端的に言えば、ある一手に対する評価値を、その手を固定してそれ以降の手を、ランダム、或いは、ある程度の思考ルーチンで、終局まで打ち尽くすことを繰り返して得られる勝率から求める手法です。これは、囲碁やオセロがある程度ランダムに打っても終局へたどり着くという、将棋などにはない囲碁の特性を利用した手法です。
11月の公開講座では、モンテカルロ木探索によって今、囲碁AIで何が起こっているかを理解し、今後の様々なゲーム開発において広く展開して行くことを目的として、研究者、開発者からこの分野で著名な3人の講師をお迎えし、最先端の技術的な内容とその効果を平易に解説して頂きます。
まずゲームAI研究全般について解説して頂き、その後、「囲碁におけるモンテカルロ木探索」の理論的背景について、そして、最後にプログラミング実装の手法について解説して頂きます。
最先端の分野においてまとまった知識を学ぶことができる貴重な機会でございますので、ゲーム開発者、この分野に興味を持つ方、そして学生の皆様に、広くご参加頂きたいと思っております。
■参考情報: 以下の資料を予習されることをお薦めいたします。
① 革新的なAI囲碁プログラム『Crazy Stone』 (wired vision)
わかりやすい形のニュースで解説されています。
http://wiredvision.jp/news/200705/2007051121.html
②「エンターテインメントと認知科学研究ステーション」
第5回招待講演
http://minerva.cs.uec.ac.jp/~ito/entcog/contents/lecture/date/20080614.html
「エンターテインメントと認知科学研究ステーション」
(伊藤毅志先生が主催)
http://minerva.cs.uec.ac.jp/~ito/entcog/
において、囲碁AIにおけるモンテカルロ木探索を扱った講演会で、モンテカルロ法の資料が充実しています。
囲碁AIにおける革命、モンテカルロ法とは何か?
(IGDA日本 y_miyakeのゲームAI千夜一夜)
http://www.igda.jp/modules/xeblog/?action_xeblog_details=1&blog_id=884
司会者(三宅)が上記の講演会に出席して書いたレポートです。
③ 羽生善治、伊藤毅志、松原仁著 「先を読む頭脳」(新潮社)
http://www.shinchosha.co.jp/book/301671/
④ 清 愼一、山下 宏、佐々木宣介著 「コンピュータ囲碁の入門」(共立出版)
http://www.kyoritsu-pub.co.jp/shinkan/shin0511_02.html
⑤ YSSと彩のページ
http://www32.ocn.ne.jp/~yss/index_j.html
※今月の公開講座より、受付時の混乱を避けるために、受付では入会および会費納入手続きを行わないこととなりました。
入会手続きはウェブサイトより行い、会費納入は銀行振り込みにてお願いいたします。
また、入会申込書もフォーマットが改定されましたので、ご確認下さい。
詳細に関しましては、下記のページをご参照下さい。
http://www.digrajapan.org/modules/eguide/event.php?eid=3
<概要>
■講師:
伊藤 毅志 (電気通信大学 情報工学科 助教)
美添 一樹 (科学技術振興機構 研究員)
山下 宏 (囲碁プログラマ)
■司会:
三宅 陽一郎 (株式会社フロム・ソフトウェア)
■予定:
18時 伊藤毅志「ゲーム情報学から見たコンピュータ囲碁」(30分)
18時30分 美添一樹「モンテカルロ木探索 理論編」(50分)
19時20分 休憩(10分)
19時30分 山下 宏「モンテカルロ木探索 実践編」(50分)
20時20分 質疑応答(20分)
20時40分 伊藤毅志「まとめ:ゲームAIのこれから」(10分)
20時50分 終了
懇親会 21時00分〜
■開催日時:
2008年11月28日(金)18:00開始 20:50終了
※受付開始時間は17:30です。
混雑が予想されますので、お早めにご来場ください。
■場所:
東京大学本郷キャンパス
※詳しい会場につきましては、決定し次第改めて会員の皆様にお知らせいたします。今しばらくお待ち下さい。
※会場が決定いたしました。ご確認ください。
東京大学工学部2号館4階246号教室
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_03_j.html
■定員:
120名(予約が定員に達した場合、当日参加受付はありません)
■参加費:
日本デジタルゲーム学会 正会員・学生会員:無料
日本デジタルゲーム学会 賛助会員(一口あたり代表者3名まで):無料
非会員:1,000円
(当日 受付にてお支払いください)
※領収書の宛名が参加登録者名義と異なる場合は、必ず下の申し込みフォームにご入力ください。入力がない場合、登録された氏名で領収書が発行されます。当日の領収書発行には応じられない可能性がございますので、よろしくお願いいたします。
■懇親会:
公開講座終了後、別会場において軽食とお飲み物を用意し、簡単な懇親会を開催する予定です。
会員間の交流を図るまたとない機会です。皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。
※懇親会費として別に1,000円を頂戴いたします
(日本デジタルゲーム学会会員含む)。