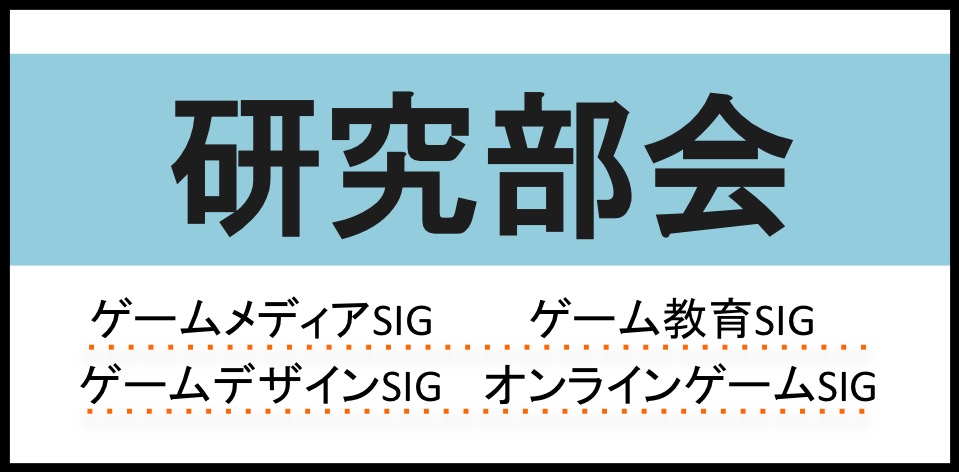投稿日:2013年7月3日
日本デジタルゲーム学会2013年夏季研究発表大会(8/31)では、会場にてポスター発表の枠を確保できました。
これに伴いまして、募集を行います。ポスター発表を申し込まれる方は、
1)名前と所属
2)発表タイトル
3)発表要旨(100~200字程度)
を添えて
summer_conferenceあっとdigra-j.net
までお申し込みください(あっとは@に変更して送信下さい) 。
締切は8月2日です。(口頭発表の申し込みは締め切っております)
大会詳細は下記をご覧ください。
投稿日:2013年6月15日
日本デジタルゲーム学会関西地域研究会は、7月5日(金)、18時から京都リサーチパークにて、
第6回DiGRA-Kを開催いたします。位置ゲーとして一世を風靡した『まちつく!』の企画運営に長きにわたって関わった中村悟氏と、『仮面ライダーウィザードGPSエンターテインメント』で京都から近畿一帯を話題に巻き込んだsupernovaの殿岡康永氏をお招きし『成功する位置ゲーの特徴と秘訣』をテーマにお話を伺います。
【概要】第6回DIGRA-K勉強会および交流会
日時 2013年7月5日(金)
18時~19時(講演会)
19時15分~21時(交流会)
会場 京都リサーチパーク 東地区 KISTIC 2階 会議室(地図)
交流会会場 エビス
講演テーマ 『成功する位置ゲーの特徴と秘訣』
登壇者 中村悟氏 すずな株式会社代表取締役 ( 代表作 『まちつく!』)
殿岡康永氏 株式会社supernova(代表作 『仮面ライダーウィザードGPSエンターテインメント』)
主催
日本デジタルゲーム学会関西地域研究会・IGDA関西・株式会社KINSHA
共催
立命館大学ゲーム研究センター(RCGS)・京都リサーチパーク株式会社
登録は公式サイトからお願いします
http://www.kinsha.co.jp/digrak/
費用:講演会無料
交流会:一般3000円、学生2500円
詳細
17時30分会場
18時00 開演
18時05~18時25分 『位置ゲーにおけるユーザー特性とゲームデザイン』 中村悟氏
18時25~18時45分 『位置ゲーで出来る産学公連携』 殿岡康永氏
18時45分~19時 ディスカッションおよび質疑応答
登壇者プロフィール
殿岡康永
京都工芸繊維大学卒業後、ソーシャルネットワーキングサービス『mixi』のプロデューサー、検索エンジン会社『百度』のプロジェクトマネージャを経て、京都太秦を拠点とする株式会社supernovaを創業。
モバイル端末に標準内蔵されているGPS機能に着目し、これらに映画やアニメなどのコンテンツを組み合わせたGPSエンターテイメント を提唱。サービスを展開してきた。代表作は、『京都妖怪絵巻』。『re:vibexTOHOKU』。『仮面ライダーウィザードGPSエンターテイメント』など。2012年にはGDCで講演している。
中村悟
2004年に営業職からエンジニア職に転身。2006年に株式会社アスク ドット
ジェーピーに入社し、検索サイトAsk.jpの開発に参画。2007年にウノウ株式会社に入社。ケータイ向けまち育成ソーシャルゲーム「まちつく!」のプロトタイプ開発を行い、2008年に「まちつく!」を一般公開。その後、「まちつく!」のmixi版、モバゲー版、スマートフォン版の開発・運用を行い、ジンガジャパン株式会社ではジェネラル・マネージャーに就任。2012年4月にジンガジャパン株式会社を退職。2012年9月に京都にて、すずな株式会社を設立。
投稿日:2012年2月25日
日本デジタルゲーム学会2011年度年次大会開催のお知らせ
テーマ:デジタルゲーム研究の地平:ゲームある日常のこれまでとこれから
開催趣旨
現在ゲーム研究は「ゲーミフィケーション」といったキーワードでも表される様にこれまで以上に様々な研究領域へと浸透をはじめています。当学会においても、関西及び中部に新たな研究会を開設したのに加え、ゲームデザインに特化した研究会の開設を視野に勉強会を続けて参りました。産業界においてもスマートフォンやタブレッドデバイスの発展により、これまで以上にゲームを気軽にプレイできる環境が整備される様になりました。
そこで、2011年度の年次大会においてはゲームそのものを対象とした研究だけでなく、その周辺領域までを視座に「デジタルゲーム研究の地平」といたしました。その結果、従来の研究内容に加え、バーチャルリアリティ、医療・福祉、産業研究、文化、開発技術など多様な研究領域の研究をこの度の年次大会において発表していただく運びとなりました。この大会をきっかけに、皆様にとってデジタルゲームの可能性とその存在意義を改めて考えるうえでの一助になることを期待しております。
日時 2012年2月25日(土)、26(日)
場所 立命館大学衣笠キャンパス充光館及び清心館他
参加費用:
非会員(一般) 3000円
非会員(学生) 2000円
会員(一般) 2000円
会員(学生) 1000円
懇親会費: 3000円
特別公開シンポジウムのみの参加:無料
日本デジタルゲーム学会2011年次大会主要日程
今年度年次大会の主要日程をお伝えします。なお個別具体的な研究発表のスケジュールについては下部のリンクを参照ください。
1.日本デジタルゲーム学会年次総会
年次総会は、25日(土)の13時00分より衣笠キャンパス内のシアター型教室、充光館301にて開催します。今回は規約改正に関する提案がございますので皆様のご参加をよろしくお願いします。
2.学会懇親会(要登録)
日時 2012年2月25日(土)
時間 18:00〜20:30
定員 70名
会場 立命館大学衣笠校舎第一体育館内
(学内食堂を貸し切ります)
3. GameonAsia連携講演The Future of Game, AI, and Computer Graphics (ゲーム、AI、CG が作る未来)
概要:
当日に同時開催されるGameonAsiaとの連携でおこなう特別講演。ゲーム技術に関係する今後の展望、とりわけ、A.I.,CGなどについて、当学会会員で株式会社スクウェア・エニックステクノロジー推進部、リードA.I.リサーチャーの三宅陽一郎氏が講演します。
日時 2012年2月25日(土)
時間 15:00~16:00
会場 充光館301
共催 立命館ゲーム研究センター
4.DiGRA Japan基調講演「デジタルゲーム産業の起源(仮)」
概要:
日本国内におけるゲーム産業黎明期についてアーケードゲームを中心に据えつつ克明
に記録した名著『それはポンからはじまった』の作者である赤木真澄氏による講演になります。
登壇者:赤木真澄氏 『それは「ポン」から始まった-アーケードTVゲームの成り立ち』筆者
コーディネータ: 岩谷 徹氏 東京工芸大学 教授
日時 2012年2月25日(土)
時間 16:20~17:40
会場 充光館301
5. 特別公開シンポジウム「ゲーミフィケーションとは何か」(要登録)
概要:
「ゲーミフィケーション」という言葉がゲーム業界内外で頻繁に聞かれるようになりました。本シンポジウムでは、モデレータに当学会会長の細井浩一教授を据え、このキーワードをテーマとした書籍を出版した方々をお招きし、筆者自身の言葉で「ゲーミフィケーション」の意義について言及していただきます。
登壇者:
藤本徹氏 東京大学特任助教
井上明人氏 国際大学GLOCOM助教
深田浩嗣氏 株式会社ゆめみ代表取締役
モデレータ:
細井浩一氏 立命館大学教授/日本デジタルゲーム学会会長
日時 2012年2月26日(日)
時間 13:00~14:30
会場 充光館301
共催 立命館大学ゲーム研究センター
詳細につきましては、各発表セッションや、立命館大学へのアクセスなどを含めた情報をPDFにして日本デジタルゲーム学会2011年次大会概要としてまとめましたのでご参照ください。
また、発表スケジュールの詳細は日本デジタルゲーム学会2011年次大会発表スケジュールを確認ください。
投稿日:2011年7月17日
日本デジタルゲーム学会では、国内ゲームデザイン研究の推進と質の向上のため、DiGRA Japanではゲームデザイン研究会を発足を検討しています。
定期的に研究会を行い、国内で行われているゲームデザイン研究をゲーム開発
者に知らせ、役立ててもらうのと同時に開発者から研究者へのフィードバック
を行うマッチングの場を提供するのが主な目的です。
以上の主旨に基づき、日本デジタルゲーム学会研究会第三回として
ゲームデザイン研究会(第二回)を開催いたします。
今回のテーマは「ゲームデザイン研究の現状」です。
日本、海外におけるゲームデザインの動向を紹介します。
■対象者
ゲーム開発者、研究者、学生、ゲーム研究に興味を持たれる方
■研究発表者募集
ゲストテーマとしてゲームデザインを中心とした学術研究発表を募集しております(発表時間は30分以内で希望する時間)。開発側の意見が伺える良いい機会なので、奮ってご参加ください。
「ゲームデザイン」という言葉は多分に曖昧な要素を含んではいますが、ここ
ではゲームプレイのために用意される遊びの仕組み全般とします。
日程:7月17日 14時~17時
会場:国際大学GLOCOM
東京都港区六本木ハークス六本木ビル2F
ホールA/B
定員数 20人 (UST放送もする予定です)
予約締切時間 2011-7-16 16:00
参加費 無料
参加登録はこちら:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dEJxWGw0MVFVZ09PdWFXLVF3Y3dRM3c6MQ
—————————————————————–
日本デジタルゲーム学会研究会第三回 – ゲームデザイン研究の現状
~研究者はゲームに求めるもの、開発者がゲームデザイン研究に求めるもの~
—————————————————————–
14:00 趣旨説明
14:10 井上明人(国際大学GLOCOM研究員)
14:40 ケネス・チャン(東京工科大学 修士課程)
15:10 ゲスト研究発表
16:10 ディスカッション
■講演内容
タイトル:ゲームデザインを「研究」するための前提
講演内容:ゲームデザインには数多く議論がなされているが、「研究」としてゲームデザインを考えていくためには何が必要だろうか。そのための前提を考えたい。
講演者:井上明人
議論演者ープロフィール:1980年生まれ。国際大学GLOCOM研究員/助教。2005年慶應義塾大学院
政策・メディア研究科修士課程修了。2005年より同SFC研究所訪問研究員。2006年より国際大学GLOCOM研究員。2007年より同、助教。2010年日本デジタルゲーム学会第一回学会賞(若手奨励賞)受賞。論文に「遊びとゲームをめぐる試論
―たとえば、にらめっこはコンピュータ・ゲームになるだろうか」など。2011年より#denkimeterプロジェクトを提唱。
タイトル:ゲームデザイン研究 ~どこから来たのか?どこに向かっているのか?~
講演内容:既存のゲームデザイン研究の全体像がどうなっているか?どのような問題を抱えているのか?産業側とのコミュニケーションギャップがなぜ存在するのか?海外究事例を紹介することを通して以上の3つの質問をアプローチし、今後ゲームデザインの研究者は何に向けて進めばよいのかを考察していきたい。
講演者:ケネス・チャン
講演者プロフィール:香港とオーストラリアで育てられた香港人。英語、広東語、北京語と日本語のクヮドリンガル。2008年にアメリカのノートルダム大学の工業デザイン学科を卒業し、2009年から東京工科大学の大学院修士課程で脳波分析を基づいてゲームデザインについて研究しています。Siggraph
Asia 2010、Nicograph International 2011などで研究発表をしている。9月卒業予定。IGDA Japan
i18n Force (Internationalization Force)の他、DiGRA
Japan研究委員会学生フェローとしてゲームデザインの学問化に向けて活動中。Global Game Jam
2011東京工科大学会場の開催にも携わっている。連絡先:@chankenneth(ツイッター)、chan.kenneth.k(あっと)gmail.com
投稿日:2011年5月14日
<予約受付は終了いたしました。沢山のご予約本当にありがとうございました。>
日本デジタルゲーム学会は
「3DC安全ガイドラインに基づく、快適な立体視ゲームの作り方」
をテーマに以下のとおり、本年第二回目の研究会を開催します
映画「アバター」の大ヒットを皮切りに、急速に普及が進む立体視コンテンツ。
デジタルゲーム産業においても、昨年PS3が立体視ゲームに本格的に対応。
今春にはニンテンドー3DSが発売と、据え置き機・携帯機双方で立体視の
時代が到来しました。アーケードゲーム機においても、立体視ゲームが続々
と登場しています。
一方で立体視コンテンツは作り方によって、また個人差によって、視覚疲労
や不快感が発生する場合があり、これまで以上に「人に優しい」コンテンツ
開発への配慮が求められます。
安全基準の一つに、3Dコンソーシアム安全ガイドライン部会による
「3DC安全ガイドライン」が存在しますが、本ガイドラインはコンテンツ
制作に関する全般的な目安を示したもので、ゲーム業界に特化された内容
ではありません。また内容については良く理解した上で、ゲーム開発への
正しい適用を行っていく必要があります。
そこで本セミナーでは、3DC安全ガイドラインの内容をゲーム開発者向けに
解説すると共に、その内容を下敷きにして、快適な3D立体視ゲームを作る
上でのポイントについて議論していきます。その上で、より実践的な
ノウハウについて、参加者と共にラウンドテーブル形式で議論を深めていきます。
なお、本会はUstreamでの配信も予定しています(録画予定なし)
概要
日本デジタルゲーム学会第二回研究会
研究テーマ:「3DC安全ガイドラインに基づく、快適な立体視ゲームの作り方」
講演者:後藤田洋伸(国立情報学研究所/情報社会相関研究系准教授)
石井源久(バンダイナムコゲームス/技術部開発サポート課)
日時:2011年5月14日(土) 14:00開始 18:00終了
*受付開始時間は13:30からです。
場所:国立情報学研究所 2009/2010室(edubaseSpace)
http://www.nii.ac.jp/
予約締切時間 2011年5月12日(木)18:00
交通アクセス
東京メトロ半蔵門線/都営地下鉄三田線・新宿線「神保町」A8出口
東京メトロ東西線「竹橋」1b出口
徒歩3~5分
<申し込み>
本文末尾の申し込みフォームより(定員になり次第終了)
申し込み締め切り: 5月11日(水) 18:00
<研究会詳細>
タイトル:3DC安全ガイドラインに基づく、快適な立体視ゲームの作り方
講師:
後藤田洋伸(国立情報学研究所/情報社会相関研究系准教授)
石井源久(バンダイナムコゲームス/技術部開発サポート課)
司会:小野憲史(ゲームジャーナリスト)
スケジュール:
13:30 開場
14:00 開会挨拶・DigraJ活動報告
14:30 講演「3DC安全ガイドラインの背景と内容」(後藤田洋伸氏)
内容解説:ゲーム開発者が知っておくべき、3D立体視の基礎知識を紹介します。また3DC安全ガイドライン策定の背景、そして内容について解説します。
15:30 休憩
15:45 講演「両眼視差方式の原理に基づく『快適な立体視』をリアルタイムゲームへ適用するには」(石井源久氏)
内容解説:「3DC安全ガイドライン」に述べられている、快適な立体視の設定をゲームに応用する手順について具体的に解説します。また「リアルタイム描画」を特徴とするゲーム独自の留意点を提示します。
16:45 休憩
17:00 パネル/ラウンドテーブル「快適な3D立体視ゲームを開発するために」後藤田洋伸氏・石井源久氏・麓一博氏(セガ開発技術部・技術開発2課)
18:00 終了
参加費:
日本デジタルゲーム学会 正会員・学生会員:無料
日本デジタルゲーム学会 賛助会員:(一口あたり申込先着3名まで)無料
非会員:1,000円
(当日、受付にてお支払いください)
参考資料:
3DC安全ガイドライン
http://www.3dc.gr.jp/jp/scmt_wg_rep/guide_index.html
3D立体視に対応しないとマイナスになる時代が来る――池尻大作氏や稲船敬二氏らが出演した,立体Expo
2010セミナー「3Dゲーム/各ゲーム会社の現状の取り組み,今後の展開」聴講レポート(4gamer)
http://www.4gamer.net/games/046/G004603/20101217002/
Imagine! The Stereoscopic 3D Games!! ~ゲームデザインから立体視を考えよう
http://cedec.cesa.or.jp/2010/program/BoF/C10_P0095.html
※当日の学会入会は受け付けておりません。入会を希望される方は、必ず開催2日前までに会員登録及び年会費の振り込みを完了させてください。
※領収書が必要な方は、入力フォームの領収書宛名欄に、(登録氏名と同じであっても)領収書の宛名をご入力ください。ご入力がない場合は、領収書は発行いたしませんので、ご了承ください。
投稿日:2011年3月6日
今回は、ゲーム研究にかかわる学部生の方々を中心に発表をおこなっていただきます。
ご都合の付く方は、どうぞ、ご参加ください。
日程:3月6日 14時~17時
会場:国際大学GLOCOM
東京都港区六本木ハークス六本木ビル2F
ホールA/B
—————————————————————–
日本デジタルゲーム学会D
2011年3月 研究会第一回 – 若手発表会
—————————————————————–
今回は、ゲーム研究にかかわる学部生の方々を中心に発表をおこなっていただきます。
ご都合の付く方は、どうぞ、ご参加ください。
日程:3月6日 14時~17時
会場:国際大学GLOCOM
東京都港区六本木ハークス六本木ビル2F
ホールA/B
申込:フォーム作成中(定員20名)
司会:井上明人(国際大学GLOCOM 助教)
発表者:
14:00 趣旨説明
14:10 松本遼祐(早稲田大学 文化構想学部 学部4年)
「デジタルゲームそのものを捉えるための試論~指標性に基づくシンクロ率~」
14:50永井良友(早稲田大学 文化構想学部 学部4年)
「語りとしてのビデオ・ゲーム」(仮)
15:30 齋藤成紀(慶應義塾大学 法学部政治学科 学部3年)
「ゲームパブリッシングとイスラーム法」
16:10 高橋志行(一橋大学大学院社会学研究科 博士後期課程)
投稿日:2010年12月18日
日本デジタルゲーム学会は、来る12月18日(土)、19日(日)に同学会初の年次大会を開催いたします。
趣旨説明
■ 共通テーマ:デジタルゲームの過去・現在・未来
「デジタルゲームに関する学術、技術の進歩発展と普及啓蒙をはかり、会員相互間および関連学協会との連絡研究の場」となることを目的として2006年に設立された本学会、国際学会DiGRA2007開催後は実際の開発者、研究者による公開講座と論文誌の発行を中心として活動をしてきました。
公開講座は平日夜の開催にも関わらず、毎回多数の参加者に恵まれ、公開講座後の懇親会も含めると夜11時過ぎまで毎回活発な議論が繰り広げられてきました。また、論文誌は刊行回数を年1回から年2回に増やして、デジタルゲーム研究の貴重な発表の場として、その役割を増しています。その熱気を受け継ぐ形で、満を持して2010年大会を開く運びとなりました。
ソーシャルゲームの隆盛や新ハード発売のニュースなど、デジタルゲームを取り巻く環境は激変が続いています。そういう時代だからこそ、原点に立ち返り、現状を丁寧に分析した研究や、デジタルゲームの根本を問い直す研究が必要となっています。
今回の大会が、皆さまにとってデジタルゲームの過去・現在・未来を考える一助になることを期待しています。
大会プログラム詳細はこちらからダウンロードしてください。
大会名称: 日本デジタルゲーム学会2010年次大会
テーマ: デジタルゲームの過去・現在・未来
主催: 日本デジタルゲーム学会
開催日時: 2010年12月18日(土)・19日(日)
両日とも9時15分~16時30分 (懇親会:18日17時~19時30分)
会 場: 芝浦工大芝浦キャンパス(306・307教室)
アクセス:http://www.shibaura-it.ac.jp/access/index.html
参加費用:
非会員(一般) 3000円
非会員(学生) 2000円
会員(一般) 2000円
会員(学生) 1000円
懇親会費:
一般4000円
学生2000円
問い合わせ窓口:次のメールアドレスまでご一報ください。
DiGRAJAPAN2010orgあっとcabsss.titech.ac.jp
(あっとは@で代替してください)
主要スケジュール
18日(土)
9:15-12:30 :発表セッション
14:00-16:30 :基調講演:鼎談:「日本ビデオゲームの黎明」
遠藤雅伸 日本デジタルゲーム学会理事(モデレータ)
岩谷徹 日本デジタルゲーム学会理事/東京工芸大学教授
石村繁一 バンダイナムコゲームス
西角友宏 ドリームス
17:00-19:30: 懇親会
19日(日)
9:15-12:30 :発表セッション
14:00-14:45 :学会総会
15:00-16:30 : 実行委員会主催シンポジウム
投稿日:2010年9月10日
日本デジタルゲーム学会関西研究会(略称、DiGRA K)
2010年9月10日(土) 17:00 開始
IGDA関西は、日本デジタルゲーム学会(以下、DiGRA Japan)、京都リサーチパーク株式会社、株式会社KINSHAとともに、DiGRA Japanとしては初となる関西での研究会、日本デジタルゲーム学会関西研究会(略称、DiGRA K)を主催することとなりました。DiGRA Japanは発足以来、主に東京にて月例会などをおこなってきました。また東京大学にて国際学会、DiGRA2007も開催しております。
この度、立命館大学映像学部副学部長の細井浩一教授が日本デジタルゲーム学会の会長代行に就任したことを受け、関西での勉強会を開催いたします。第一回となるこの度はゲーム業界の未来を見据えるということ、並びに業界との強い連携関係を示すということからIGDA日本代表兼DiGRA Japan理事のゲームジャーナリスト新清士が「世界のゲームシーンが示唆するゲーム業界の進むべき道」をテーマに講演いたします。
以下、DiGRA Kの開催概要です。
日時 2010年9月10日(金)
時間 17:00-18:30
場所 京都リサーチパークサイエンスホール
シンポジウム参加:無料。ただし、登録が必要です。 (交流会:社会人3000円、学生2000円)
想定される観客層:ゲーム開発者並びに研究者、ゲーム業界志望者など
参加予定数 最大 150名
主催 日本デジタルゲーム学会・IGDA関西・京都リサーチパーク株式会社・株式会社KINSHA
1.目的
デジタルゲームは日本コンテンツ産業におけるパイオニアとして世界に広がり、まさにCool Japanを代表するメディアへと成長を果たしました。同時に各国との熾烈な競争や、プラットフォームの多様化、カジュアルゲームの流行による新規参入など業界全体に激震が走り続けていています。同時にハードウェアならびにメディアの劣化現象により文化としてのゲームがまさに失われようとしているという現状もあります。当研究会はこれらを踏まえ、勉強会や交流会を通して過去の総括と未来への展望を追及していく所存です。
2.構成
第一部
ゲーム開発者や研究者による講演やディスカッション
17:00-17:30 「DiGRA K 発足にあたり」細井浩一教授 DiGRA Japan 代表代行
17:30-18:30 「世界のゲームシーンが日本のゲーム産業に示唆するもの」新清士 IGDA 日本 代表
第二部
19:00-21:00 交流会(YEBiSU Japanese Dining Café&Bar http://www.cafe-yebisu.com/ )
3.申込方法
下記宛に
1参加者氏名、2所属、3メールアドレス、4交流会への参加有無
をご記入の上お送りください。
digrak@kinsha.co.jp
投稿日:2010年4月3日
「GDC(Game Developers Conference)2010報告会」
2010年4月3日(土) 13:00 開始
IGDA(国際ゲーム開発者協会)日本は、3月9日〜13日に米サンフランシスコで開催されたGDC(Game Developers Conference)2010の報告会を2009年4月3日(土)に行います。
お申込方法は下記URLをご参照ください。
http://www.igda.jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=276
今年のGDCは、事前の予想とは裏腹に、結果的に見ると、昨年の参加者数を1,500人上回る18,500人もの参加がある過去最大規模のものになりました。ソーシャルゲームの台頭を中心としたものが大きなトピックとなり、ゲーム産業の方向性の変化を物語る内容になりました。一方で、「アンチャーテッド2」の多数の講演など、ハイエンド向けのゲームも一つの到達点を示した時期でもありました。
これらの内容を、実際に参加された方の報告という形で、情報をお伝えさせて頂きます。
これらを、今回は、10名の方にご報告頂きます。生の多様な産業の情報を得る機会として、ぜひご利用ください。
<概要>
■日時 :2009年4月3日(土) 13:00 – 18:30 (受付 12:30 – 14:00)
■場所 :東京大学本郷キャンパス 情報学環・福武ラーニングシアター
(情報学環・福武ホール地下2階)
(地図)http://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/access.html
■主催 :国際ゲーム開発者協会日本(IGDA日本) http://www.igda.jp/
■共催 :日本デジタルゲーム学会(DiGRA Japan) http://www.digrajapan.org/
■定員 :200名
■参加費:2,000円(入場券チケットを購入して下さい)
日本デジタルゲーム学会 正会員・学生会員:無料(当日に返金)
日本デジタルゲーム学会 賛助会員(一口あたり代表者3名まで):無料(当日に返金)
※日本デジタルゲーム学会会員の方にも事前にチケット代金をお支払いいただく必要がございます。
※日本デジタルゲーム学会会員の方は当日、会員であることを確認した後、チケットと引き換えに参加費を返金致します。ご了承ください。また、チケット郵送費につきましては返金を行いませんので、ご注意ください。
※期限切れでない有効なIGDAメンバーシップをお持ちの方は、当日、メンバーシップカードをお持ち下さい。チケットと引き換えに参加費を返金します。ご了承ください。
■懇親会費:3,500円
(上記の入場券チケットと合わせて、全席自由チケットを購入して下さい)
※チケット購入情報は本稿末尾をご覧下さい。
□スケジュール (アップデートされます)
※スケジュールは予定です。告知なしに変更される場合があります。
13:00-13:30 「IGDAのアップデート情報、ソーシャルゲーム関連紹介」
新清士(IGDA日本、ジャーナリスト)
13:30-14:00 「(仮)男性にも女性にも人気が出るゲームの根拠セッションから&GDCパンの結末」
大前広樹( KH2O)
14:00-14:30 「(仮)ローカライゼーションサミット概要。文化変化の実情」
小野憲史(ジャーナリスト)
<休憩>
14:45-15:15 「多様なゲームの可能性?米国におけるインディーズを中心に?」
井上明人(GLOCOM研究員)
15:15-15:45 「(仮)大型タイトル関連のセッションから」
佐藤カフジ(ジャーナリスト)
15:45-16:15 「(仮)グラフィックス技術関連セッションから」
岩出敬(セガ)
<休憩>
16:30-16:45
(予定)
16:45-17:15 「先端グラフィックス関連技術セッションから」
西川善司(トライゼット)
17:15-17:45 「具体的な事例報告が増えたAIセッションから」
三宅陽一郎(フロム・ソフトウェア)
17:45-18:30 ディスカッション「今後のゲーム産業の方向性」
■懇親会 (別会場) 19:00-
投稿日:2010年2月18日
「メディアの変遷とゲームジャーナリズムの変化」(DigraJ公開講座10年2月期)
2010年2月18日(木) 18:30 開始
デジタルゲーム産業は、ゲーム情報を伝えるマス・メディアと共に発展して来た歴史を持ち、ゲームジャーナリズムはこれまでゲーム産業で大きな役割を果たして来ました。
その情報はユーザーにゲーム情報やゲームの楽しみ方を伝えると共に、ユーザーの間でゲーム情報を共有し、「ゲームについて語る」という文化を産み出して来ました。
雑誌、インターネット・サイト、ラジオ、DVD、動画配信、twitterなど、メディアの変化・発展と共に、双方向のメディア時代に適応しつつ、ゲーム情報を伝えるメディアは、求められる役割を果たしながら、多様化し、より一層の発展を続けています。
本セミナーでは、こういったゲームジャーナリズムの歴史的変化を明確に捉えるため、こういった変化と共にキャリアを積まれて来たゲーム雑誌、ゲームサイトの編集者、ジャーナリストの皆様を講師に迎え、各自の経験に即した歴史的な変遷を講演して頂きます。そして、お互いの視点を共有しつつディスカッションを行い、これからのゲームジャーナリズムの展望を描き出したいと思います。
皆様のお越しをお待ちしております。
※このページの末尾に予約申し込みフォームがあります。
当日までに予約が満席でない場合に限り、当日参加も可能です。
<概要>
■タイトル:
「メディアの変遷とゲームジャーナリズムの変化」
■講師:
川口 洋司
(株式会社コラボ代表取締役、一般社団法人日本オンラインゲーム協会事務局長、元「Beep」編集長)
渡辺 一弘
(株式会社スパイク プロデュース部 プロデューサー)
編集者歴
1993年~1997年 ソフトバンク時代 (Theスーパーファミコン→Theプレイステーション)
1999年~2006年 ソニー・マガジンズ時代 (ハイパープレイステーション
船津 稔
(GAME Watch編集部)
■開催日時:
2010年2月18日(木) 18:30開始 21:00終了
※受付開始時間は18:00からです。
■場所:
東京大学本郷キャンパス 工学部新2号館9階92B教室
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_03_j.html
■司会:
井上 明人
(GLOCOM 研究員/助教)
小野 憲史
(ゲーム・ジャーナリスト、DiGRA JAPAN 学会員、元「ゲーム批評」編集長)
三宅 陽一郎
(株式会社フロム・ソフトウェア、DiGRA JAPAN 研究委員)
※問い合わせ先: 三宅 y.m.4160(あっと)gmail.com
■企画協力:
小野 憲史
■タイムテーブル
年代順に沿って講演して頂きます(各30分)
80年代編
川口 洋司「ゲーム情報メディアの創世期から成長期まで」
90年代編
渡辺 一弘 「ゲームメディアの成熟と転換」
休憩(15分)
00年代編
船津 稔「ウェブメディアの登場と拡散」
パネルディスカッション・質疑応答
パネル司会:井上 明人
■講演内容
川口 洋司
「ゲーム情報メディアの創世期から成長期まで」
[概要]
1985年コンシューマーゲーム市場の成立とともに誕生したゲーム情報誌。
その成り立ちからゲーム誌黄金時代に至るまでのメディアの推移と役割を解説する。
渡辺 一弘
「ゲームメディアの成熟と転換」
[概要]
80年代の第一次創刊ラッシュを経て、プレイステーションの登場を境に第二次創刊ラッシュを迎えたゲーム雑誌の変遷と果たした役割について、当時のトピックスを追いながら解説します。
船津稔
「ウェブメディアの登場と拡散」
[概要]
2000年代に入りインターネットの広がりと共にWEB上におけるメディアが登場。
拡大していく中で、我々はなにを伝えることができたのか。
さらにはインターネットの技術の進歩に合わせ、広がりを見せる情報流通の中、我々はなにを行なうべきかを探りたいと思います。
■定員:
120名
(予約が満席の場合は、当日参加受付はございません。また、当日参加の方は受付でお待ち頂く場合がございます。ご了承下さい。)
■参加費:
日本デジタルゲーム学会 正会員・学生会員:無料
日本デジタルゲーム学会 賛助会員:(一口あたり申込先着3名まで)無料
非会員:1,000円
(当日、受付にてお支払いください)
※当日の学会入会は受け付けておりません。入会を希望される方は、必ず開催2日前までに会員登録及び年会費の振り込みを完了させてください。
※領収書が必要な方は、入力フォームの領収書宛名欄に、(登録氏名と同じであっても)領収書の宛名をご入力ください。ご入力がない場合は、領収書は発行いたしませんので、ご了承ください。